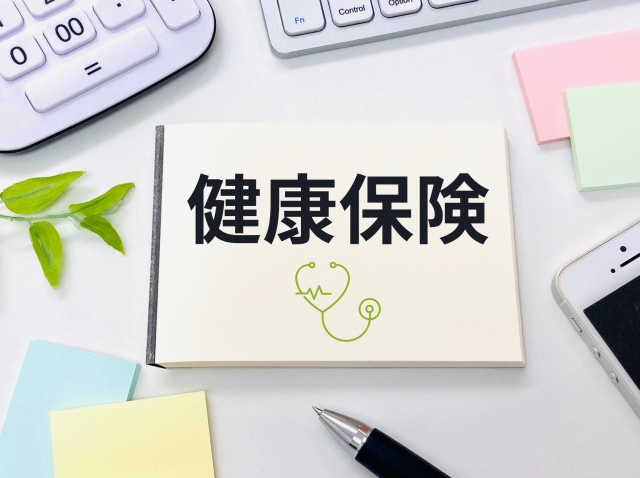少子化対策の流れの中で、育児をする就労者に対する支援の制度が充実してきた。
雇用保険法上の育児に関する給付としては、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金の制度がある。また、2025年(令和7年)4月1日施行の改正により、出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金が新設された。
育児休業給付金は、被保険者(一般被保険者又は高年齢被保険者)が、1歳未満(保育施設に空きがない等の事情があれば2歳まで延長が可能)の子に係る育児休業をした場合に支給される給付である。また、出生時育児休業給付金は、被保険者が、その子の出生後8週間以内(原則)に4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(「出生時育児休業」)をした場合に支給される給付である。
これに対し、新設された出生後休業支援給付金は、被保険者及びその配偶者の両者(原則)が、子の出生直後の一定期間(具体的には、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に14日以上の出生後休業を取得する場合に、28日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額が支給されるものである。育児休業給付金(180日までは支給率67%)と併せて休業開始前賃金の80%相当額が支給されることになる。これに加え、産前産後休業期間中及び育児休業期間中は健康保険料・厚生年金保険料の免除の制度が適用されるため、出生後休業の期間中は実質的に休業前の手取り賃金がほぼ保証されることになる。
さらに、育児時短就業給付金は、被保険者がその2歳未満の子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(育児時短就業)をした場合に、育児時短就業中の各月(1支給対象月)に支払われた賃金額の10%を上限として支給される時短就業に係る給付である。
これらの育児休業等給付は、元来、被保険者の雇用継続を図る制度である。被用者が育児休業をする権利は育児介護休業法によって認められている。しかし、事業主が育児休業期間及び産前産後休業期間に賃金を支払う法令上の義務はなく、特段の合意がない限り、当該期間中は無給となる。そこで、育児休業期間中の所得保障を図ることにより、育児休業を取得し易くするとともに、育児休業者の失業を防止しその雇用の継続を図るために、育児休業給付が設けられた。
新設された出生後休業支援給付は、夫婦の共働きと「共育て」を支援するために、育児休業期間中の育児休業給付の上乗せを図るものである。これに対し、育児時短就業給付は、育児のために所定労働時間を短縮して就業(育児時短就業)した場合に賃金の一定額を支給するという時短就業に係る給付の制度であるが、いずれも出産・子育てに取り組む家庭を支援する制度である。
法の規定や頻繁に変わる通達の内容など、複雑でなかなかわかりにくいものです。ご自身で確認するよりは専門家に聞いた方が早い場合も多々あります。ご質問、気になることなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
⇓