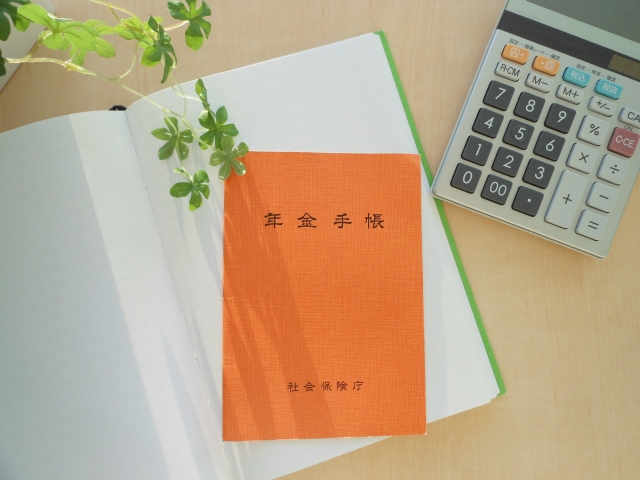
遺族厚生年金の見直しが行われることになった(2025年6月に改正法案が成立)。男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されるが、大まかにいえば現行制度が男女で扱いに大きな差があるのが、見直し後は男女共通の制度に変わる。
とりあえず押さえておきたいのは、以下のような人にとっては現在と変更がないということだ。
・ 60歳以上で死別した人
・ 子ども(18歳になった年度末まで又は障害の状態にある20歳未満)を養育する間にある人
・ 改正前から遺族厚生年金を受給していた人
・ 2028年度に40歳以上になる女性
改正の実施までにまだ少し時間があるが、ここで遺族厚生年金制度について基本を確認しておきたい。まず、受給要件のうち、死亡者の要件である。
遺族厚生年金の支給を受けるためには、亡くなった人(死亡者)が特定の要件を満たしている必要がある。この死亡者に関する要件は、大きく分けて①被保険者等の死亡と、②保険料納付要件の2つから構成される。
① 被保険者等の死亡の要件
まず、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が、以下のいずれかに該当して死亡したことが必要である。この要件は、年金加入期間の長さに応じて「短期要件」と「長期要件」に大別される。
(A) 短期要件
原則として、老齢厚生年金の受給資格期間(25年以上に限る)を満たしていない人が死亡した場合の要件。以下の3つのケースが該当する。
1.厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
現在、厚生年金保険に加入中の人が亡くなった場合である。行方不明となり法律上の失踪宣告を受けた人で、行方不明になった当時に被保険者であった場合も含まれる。
2.被保険者資格を喪失した後に、特定の傷病で死亡したとき
厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、被保険者であった間に初診日がある傷病が原因で、その初診日から5年以内に死亡した場合である。例えば、病気のために会社を退職し、その後まもなくその病気が原因で亡くなった、といったケースがこれにあたる。
3.障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
障害の程度が1級または2級に該当する障害厚生年金を受給していた人が亡くなった場合である。3級の障害厚生年金の受給権者が亡くなった場合は、この要件には該当しない。
(B) 長期要件
原則として、老齢厚生年金の受給資格期間25年以上を満たしている人が死亡した場合の要件である。
4.老齢厚生年金の受給権者などが死亡したとき
受給資格期間25年以上の人が亡くなった場合である。この場合の受給資格期間には、保険料納付済期間、保険料免除期間のほか、合算対象期間、65歳以上の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。なお、この「25年」という期間については、生年月日などに応じて期間が短縮される「受給資格期間の短縮特例」が適用される場合がある。
② 保険料納付要件
短期要件のうち、上記(A)の1と2のケースに該当する場合は、亡くなった人が死亡日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要がある。
原則(3分の2要件)
死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間(保険料納付済期間)と保険料の納付を免除された期間(保険料免除期間)を合わせた期間が、全体の3分の2以上であること。
特例(直近1年要件)
令和8年4月1日前に死亡した場合、死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、死亡時に65歳以上の人にはこの特例は適用されない。
なお、短期要件(A)の3(障害厚生年金受給権者の死亡)と長期要件(B)の4の場合は、すでに年金受給権の発生時や長期間の加入実績によって保険料納付が確認されているため、死亡時に改めてこの保険料納付要件が問われることはない。
亡くなった人が短期要件と長期要件の両方を満たす場合(例:厚生年金に加入中で、かつ受給資格期間が25年以上ある方が死亡した場合)は、遺族が特に申し出をしない限り、原則として短期要件に該当するものとみなされる。これは、短期要件の方が、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合に年金額を300月分で計算する「最低保障」が適用されるなど、遺族にとって有利になるケースが多いためである。
法の規定や頻繁に変わる通達の内容など、複雑でなかなかわかりにくいものです。ご自身で確認するよりは専門家に聞いた方が早い場合も多々あります。ご質問、気になることなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
⇓
