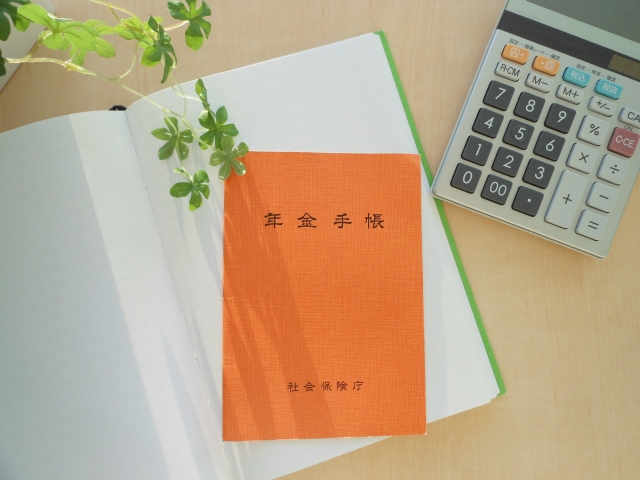
遺族厚生年金制度の基本について、今回は受給対象者(遺族)の要件である。遺族厚生年金は2028年度から制度の一部が変更になる予定だが、ここでは現行制度を確認する。
遺族厚生年金は、誰でも受け取れるわけではない。受給するためには、死亡者の年金加入状況などの要件に加えて、受け取る側である「遺族」にも細かな要件が定められている。
まず、遺族厚生年金を受け取るための最も基本的な考え方を2つ押さえておく。
①大前提:死亡者に「生計を維持されていた」こと
遺族厚生年金の対象となるのは、死亡者によって生計を維持されていた遺族である。これは、すべての遺族に共通する大前提の要件である。
「生計を維持されていた」とは、具体的には、死亡者と生計を同じくしており、かつ、遺族自身の収入が一定の基準を満たしている状態を指す。
生計同一の要件:原則として、住民票上、同一世帯に属している場合に認められる。単身赴任や就学、病気療養などで住民票が別になっていても、生活費や療養費などの経済的な援助が行われていたり、定期的な音信や訪問があったりした場合は、生計を同じくしていたと認められることがある。
収入の要件:原則として、前年の収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であることが必要。この金額以上の収入がある場合は、原則として生計を維持されていたとは認められない。
②受給できる遺族の範囲と優先順位
遺族厚生年金を受け取れる可能性がある遺族の範囲は法律で定められており、「配偶者、子、父母、孫、祖父母」に限られる。注意点として、兄弟姉妹は遺族厚生年金の対象には含まれない。
さらに、これらの遺族の中で、最も優先順位の高い方一人が年金を受け取ることができる。つまり、対象となる遺族が複数いる場合でも、全員が同時に受け取れるわけではない。
優先順位は以下のとおり。
第1順位:配偶者、子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母
例えば、死亡者に配偶者と父母がいた場合、優先順位が高い配偶者が受給権者となり、父母は遺族厚生年金を受け取ることはできない。
受給要件をさらに詳しくチェック
ここからは、遺族の関係性ごとに、具体的な受給要件を詳しく見ていく。妻以外の遺族には、前述の「生計維持要件」に加えて、年齢や障害に関する要件が加わるため、注意が必要である。
配偶者(妻・夫)の要件
配偶者には、法律上の婚姻関係にある者に加え、事実婚(内縁関係)の者も含まれる。ただし、現行制度では、妻と夫では要件が大きく異なる。
妻の場合
夫が亡くなった場合、妻は年齢にかかわらず、生計維持要件を満たしていれば受給資格者となる。特別な年齢要件はない。
ただし、注意すべき点として、夫の死亡当時に30歳未満で、かつ子(遺族基礎年金の対象となる子)がいない妻の場合、受け取れる遺族厚生年金は5年間の有期給付となる。これは、若く、子のいない妻は再就職などによって自立した生活を営むことが可能であるという考え方に基づいている。
夫の場合
妻が亡くなった場合、夫が遺族厚生年金を受け取るためには、生計維持要件に加えて、妻の死亡当時に55歳以上であるという年齢要件を満たす必要がある。
さらに、支給開始年齢にも注意が必要である。55歳で受給権を得たとしても、原則として年金の支給が開始されるのは60歳からとなる。つまり、55歳から59歳までの間は支給停止となるのが基本である。
【例外】
ただし、夫が遺族基礎年金もあわせて受給できる場合(=亡くなった妻との間に18歳年度末までの子などがいる場合)には、60歳を待たずに55歳から遺族厚生年金を受け取ることができる。
子・孫の要件
子や孫が遺族厚生年金を受け取るためには、生計維持要件に加えて、以下のいずれかの要件を満たし、かつ「現に婚姻をしていない」ことが必要である。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあること
- 20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にあること
なお、亡くなった当時にまだ生まれていなかった胎児も、無事に出生した場合は、将来に向かって遺族厚生年金の対象となる子とみなされる。
父母・祖父母の要件
父母や祖父母が遺族厚生年金を受け取るためには、生計維持要件に加えて、夫の場合と同様に死亡者の死亡当時に55歳以上であることが必要である。
また、支給開始年齢も夫の場合と同様で、原則として60歳に達するまで支給は停止される。ただし、夫に設けられているような遺族基礎年金を受け取る場合の例外規定は、父母・祖父母にはない。
誰が優先される?遺族間の優先順位のルール
前述の通り、遺族厚生年金は最も優先順位の高い遺族一人が受給権者となる。ここでは、少し複雑な優先順位のルール、特に配偶者と子の関係について確認する。
配偶者と子の複雑な関係
法律上、配偶者と子は同順位とされている。しかし、両方が受給要件を満たす場合、どちらか一方が優先して支給を受け、もう一方は支給停止となる調整が行われる。
原則
配偶者が遺族厚生年金の受給権を持つ期間は、子の遺族厚生年金は支給停止となる。つまり、通常は配偶者(妻または夫)が優先的に年金を受け取ることになる。
例外
配偶者が遺族基礎年金を受けられず、子が遺族基礎年金を受けられる場合(例えば、離婚後に親権者である元配偶者に引き取られていた子がいるケースなど)は、子の遺族厚生年金が優先され、配偶者の年金が支給停止されることがある。
転給制度はない
日本の遺族年金制度には、労災保険の遺族(補償)等年金にあるような「転給」という仕組みはない。
これは、一度、先順位の遺族が受給権を取得した場合、その者が後に結婚や死亡などで受給権を失ったとしても、後順位の遺族(例えば父母や祖父母)に受給権が移ることはない、ということを意味する。最初に受給権者が決まった時点で、それより後順位の遺族は受給資格者ではなくなる。
まとめ
遺族厚生年金の受給対象者となるための「遺族の要件」は、死亡者との続柄、年齢、子の有無、障害の状態などによって非常に細かく定められている。
【ポイントの再確認】
- 大前提は、亡くなった人に生計を維持されていたこと。
- 対象は配偶者、子、父母、孫、祖父母のみ。
- 妻には年齢要件がないが、夫・父母・祖父母には55歳以上という要件がある。
- 夫・父母・祖父母は原則60歳まで支給停止となる。
- 配偶者と子は同順位だが、原則として配偶者が優先される。
- 一度受給権者が決まると、後順位の者に権利が移る転給はない。
法の規定や頻繁に変わる通達の内容など、複雑でなかなかわかりにくいものです。ご自身で確認するよりは専門家に聞いた方が早い場合も多々あります。ご質問、気になることなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
⇓
