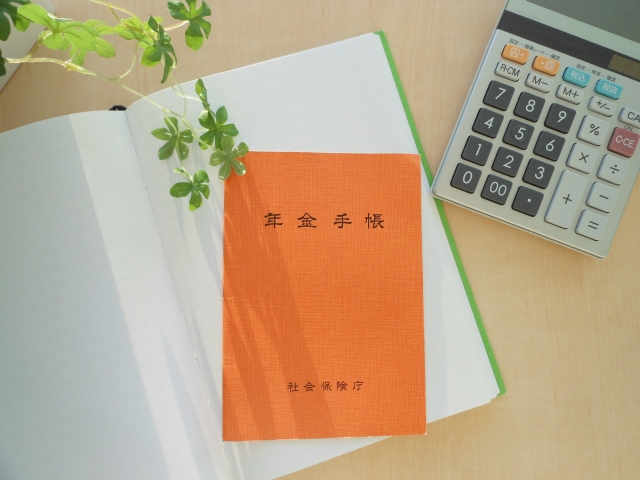
老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を有する者が原則として65歳以上となり、受給資格期間(国民年金法に定める保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間、特例として、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間)が10年以上である場合に、被保険者であった期間の平均標準報酬額(又は平均標準報酬月額)と被保険者期間の月数によって計算される額その他の額が支給される年金制度である。一般的には、適用事業所に使用される労働者が、その受ける報酬の額に従って雇用者と折半した保険料を納付し、その使用された期間に従って、老齢期に老齢基礎年金の上乗せとして老齢厚生年金を受給するというのが典型的な形である。臨時に使用される者や一定の短時間労働者などの適用除外者に該当しない労働者は、適用事業所に使用される限り、70歳に達するまでは被保険者となる(その他、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であっても、事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けて、単独で任意加入できる制度なども定められている)。
被保険者期間があり受給資格期間を満たす者は、65歳に達すると受給権が発生し、支給の繰下げの申出をしない限り、65歳に到達した時点で計算される額の年金を受給することになる。その時点での年金額に考慮されるのは、受給権を取得する月の前の月までの被保険者であった期間である。一方、70歳未満の受給権者が年金を受給しながら引き続き適用事業所に使用される等により被保険者となることが可能であり、年金を受給しながら働き、被保険者期間を増やすことによって、将来の年金額を増加させることができる(ただし、在職老齢年金の制度により、在職中は総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が一定額を超えると年金額の一部が支給されなくなる)。受給権者が引き続き被保険者である場合、増加した年金額はいつの時点で計算され、いつから受給できるのかが問題となる。
厚生年金保険法では、年金額の改定に関するルールの一つとして、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするといういわゆる退職時改定の制度が定められている。そして、被保険者である受給権者が退職し、被保険者の資格を喪失した場合は、その資格喪失事由に該当するに至った日(つまり退職日)から1月を経過した日の属する月から、年金額が改定されることになっている。例えば3月末日に退職すれば、翌4月の分から改定された年金額を受給できることになる(起算日3月31日の応当日が4月にないため4月末日が1月の期間の満了日となり、同末日が1月を経過した日と取り扱われている)。資格喪失事由には、退職(使用される事業所に使用されなくなったとき)のほか、任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、又は、適用除外者に該当するに至ったときも含まれ、これらの場合の扱いは退職時と同じである。また、70歳に達したときも、その日に被保険者の資格を喪失するが、その場合、被保険者資格を喪失した日(つまり70歳の誕生日の前日)から起算して1月を経過した日の属する月から年金額が改定される(被保険者が死亡した場合は、老齢厚生年金の受給権は消滅するので、年金額を改定する意味はない)。
社会保険制度の細部の規定や頻繁に行われる見直しの内容など、複雑でなかなかわかりにくいものです。ご自身で確認するよりは専門家に聞いた方が早い場合も多々あります。ご質問、気になることなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
⇓
