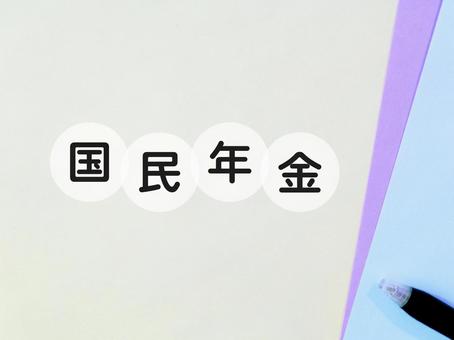老齢基礎年金は、原則として65歳に達したときに、10年以上の受給資格期間(基本的には保険料納付済期間と保険料免除期間)を満たしていれば、受給権が発生する。しかし、さまざまな事情でそれよりも早く老齢年金給付を必要とする個々のケースに配慮して、60歳から64歳の間に支給を開始できるようにしたのが、老齢基礎年金の支給繰上げの制度だ。(その反対に、老齢基礎年金の支給開始を66歳到達日(又は受給権取得日から1年を経過した日)以後に遅らせる、繰下げの制度もある。)
年齢以外の支給要件を満たしている60歳代前半の者は、支給の繰上げを請求することにより、減額された老齢基礎年金の支給を受けることができる。
繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、65歳からの老齢基礎年金の額(繰上げ請求をする者の保険料納付済期間等に応じその者が65歳から支給を受けられる額)から、政令で定める一定額を減額した額とされており、具体的には、昭和37年4月2日以降に生まれた者について、繰り上げる期間に応じて1月あたり1000分の4(0.4%分)が減額される。
なお、この減額率は、昭和37年4月1日までに生まれた者については、1月あたり0.5%であり、2022年(令和4年)4月施行の改正により、施行日(令和4年4月1日)の前日に60歳に達していない者(つまり昭和37年4月2日以降生まれの者)については0.4%とすることに改められた。従来よりも減額幅が小さくなるということであり、支給繰上げの制度がより使いやすくなった。ちなみに、昭和16年4月1日以前生まれの者は、更に減額率が高く、また、算定方法も異なっていた。
減額率の合計は、支給繰上げを請求した月から65歳に到達する月の前月までの月数に0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)を乗じて得た率となり、例えば60歳に到達した月に支給繰上げの請求をすると、0.4%x60月=24%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%x60月=30%)が減額され、当該減額された年金額を生涯受けることになる。繰上げ請求の時期を遅らせれば、それだけ減額幅も小さくなる。
支給の繰上げを請求すると、その請求があった日にその者に「老齢基礎年金を支給する」ことになっている。その意味は、請求した日(実際には請求書が受理された日)に当該請求した者に老齢基礎年金の受給権が発生するということであり、実際の支給は、年金の支給の原則に従い、受給権の発生した日の翌月分からが支給対象となり、偶数月にその前月までの分が支払われる(2月分と3月分は4月に、4月分と5月分は6月に、というように、通常は2か月分まとめて支払われる)。
社会保険制度の細部の規定や頻繁に行われる見直しの内容など、複雑でなかなかわかりにくいものです。ご自身で確認するよりは専門家に聞いた方が早い場合も多々あります。ご質問、気になることなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
⇓