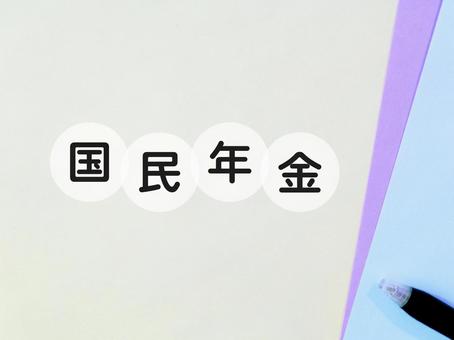老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者が65歳に達し受給権が発生すると、受給権者は、裁定の請求を行い、厚生労働大臣による裁定を受けて、年金を受給できるようになる。裁定とは、年金の受給権の発生要件を満たしているかどうかや、年金の金額等について、保険者(政府)が公権的に確認をする行為で、政府の画一公平な処理により無用の紛争を防止し、給付の法的な確実性を担保するために行うものと解されている。具体的には、受給権者が市町村や日本年金機構に裁定請求書を提出することによって行う。
一方、65歳からすぐに年金を受給せずに、支給開始の時期を遅らせ、割増しされた額の年金を受給する支給の繰下げも認められている。支給の繰下げは、65歳で受給権を取得した者が66歳に達する前に裁定請求をしていない場合(あるいは65歳以降に受給権を取得してから1年間裁定請求をしていない場合)に、66歳に達する日以後(受給権取得日から1年を経過した日以後)に支給繰下げを申し出て、増額された老齢基礎年金の支給を受けられる制度である。
増額率は1か月当たり1000分の7(0.7%)で、受給権を取得した日の属する月から支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数を乗じて計算する。例えば65歳到達時に受給権を取得した者が70歳に達した月に支給繰下げの申出をすると、0.7%x60月=42%となり、申出をした日の翌月分から支給が行われ、その者の保険料納付済期間等に応じその者が65歳から支給を受けられる本来の額に42%増額加算された年金額が支給される。
支給繰下げができる期間の上限は、以前は60月、つまり基本的には70歳到達(又は受給権取得の5年後)までであったが、2022年(令和4年)4月施行の改正で、120月、すなわち75歳到達(受給権取得の10年後)までに引き上げられた。この改正は、施行日(令和4年4月1日)の前日において、70歳に達していない者(又は、施行日の前日において老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者)について適用される。したがって、一般的には1952年(昭和27年)4月2日以後生まれの者が対象となる。改正後は、65歳で受給権を取得した者が75歳に到達した月以降に支給繰下げの申出をすると、繰下げができるのは最大120月までとなり、75歳に達した日に申出があったものと見なされ、0.7%x120月=84%の増額をした年金額を受けることになる。
なお、75歳(上記の改正前は70歳)に達する日より前に他の年金給付(老齢年金給付や付加年金以外の年金給付のこと、具体的には障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等)の受給権者となった者は、当該他の年金給付の受給権の取得日に老齢基礎年金の支給の繰下げの申出があったものと見なされ、老齢基礎年金はその時点での増額率に基づき計算された額が翌月分から支給される(ただし、他の年金給付との併給の調整により支給停止となる場合もある)。また、66歳に達する日(受給権取得日から1年を経過した日)前に他の年金給付の受給権を取得した場合には、老齢基礎年金の支給の繰下げを申し出ることはできない。
社会保険制度の細部の規定や頻繁に行われる見直しの内容など、複雑でなかなかわかりにくいものです。ご自身で確認するよりは専門家に聞いた方が早い場合も多々あります。ご質問、気になることなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
⇓